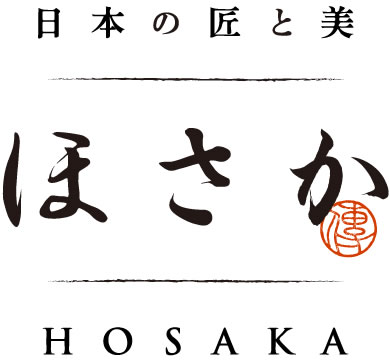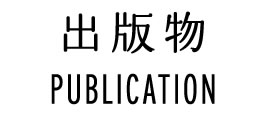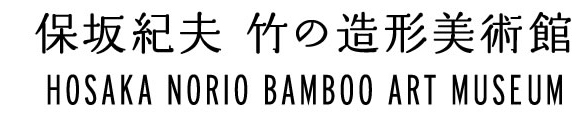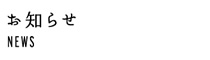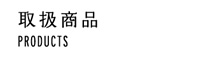今日8月4日は平日月曜日で通常は休館日ですが、1つの理由ともう1つ母の命日ということもあり、特別に開館日にしました。
母が亡くなって、もう9年。
毎年書いているのではないかと思いますが、間違いなく人生で最も辛い、いや、「辛い」という言葉を遥かに超えた信じられない突然死で、現実として受け止めること、正常な心を保つことが難しかったです。
当時は、もう今後の人生これ以上辛いことは無いだろう、と思ったのですが、これでもかと色々あります(笑)。
「自分の未熟さ」と「難しいことに挑戦を続けている」のと「何人分もの志事をしている」からだと思います。
竹の解説ツアーを必ず私が行っているのは、理由があります。
両親の息子は、世界に私しかいないからです。
ツアーでは作品の解説だけではなく、息子しか話せない家族・母の話もします。
当然、息子の生解説ツアーは、私が生きているうちしかできませんから、未体験の方はなるべく早くお越しください(笑)。予約制にして解説ツアーを始めて8年目となり、私がこの世を去った時に、「貴重だったね」と言っていただける内容だと自負しています。
休館日を特別に開館したら、素晴らしい出会いがありました。
その方のご感想です。
「本当にありがとうございました![]() お父さま保坂紀夫さまの圧倒的な作品群を前にして、言葉が見つかりません。人間の想像力や創造力、神さまレベルの手仕事の凄さにも言葉がありません。
お父さま保坂紀夫さまの圧倒的な作品群を前にして、言葉が見つかりません。人間の想像力や創造力、神さまレベルの手仕事の凄さにも言葉がありません。
あの場(工芸品のツアー)で伺ったお話も大変に考えさせられる本質的な内容ばかりに圧倒されました。是非また再訪させて頂きます![]() 」
」
「「竹の造形美術館」は、間違いなく異次元への入り口。この美術館の全てが、保坂さんのお父さま保坂紀夫氏とお母さまのお二人が創造されたものであることを感得しました。」
ご一緒された方も
「奇跡的な作品たちは、言葉を越えてる![]() 」「すべて完璧だった1日」というご感想でした。
」「すべて完璧だった1日」というご感想でした。
ツアー終了後も、色々なお話を伺ったり、「八方良し」の講演会や寺子屋、かいまみ(情報誌)、日本の伝統、社会のことなど話をすることができました。
「これだけ多くの活動をしている人(私)には、支えが絶対に必要。素晴らしい活動をしているのだから、そういう人が絶対に出てくる」と仰っていただきました。
竹の解説ツアーの中で、「母の支えがなければ、父はこれだけの作品を残すことは絶対できなかった」とお伝えしています。偉業は、一人では為し得ない。
父を支えることも、寝たきりになった祖父の介護など大変だったと思いますが、母はやり遂げました。私は当時ダメ息子だったと思いますが、甲府の店で働き、多額の借金を返済してきたので、少しは支えられたかと思います。
店を始めてくれたこと、継がせてくれたこと、父に感謝しています。
母と24年間、店を一緒にできたことも幸せなことでした。
私自身も今になり、店や父の作品・仕事がどれほど貴重なものか、という価値を理解できるようになりました。
9月18日(木)に二人の追悼企画を行いますので、ぜひご参加ください。
「工芸品の解説体験+昼食+竹の作品解説+保坂紀夫生前の映像+ピアノ・ハープ・ソプラノのコンサート」
https://fb.me/e/iwQvUxubA
「協力は強力」
うちに限らず、家族経営というのは理想的だと思っています。私達が幸せに暮らせるか、良い社会を作っていけるか、は、家族や仲間と協力できるか、助け合えるか、にかかっていると思います。
だからこそ、支配者層は、「領土問題」「原発」「基地」「男と女」「核家族」「選挙」など分断工作を行い続けてきたわけで、最近では感染騒動を創作して「集まるな、離れろ」と露骨にやってきました。
今の日本は、地域や社会が壊れていっています。
地域・社会が壊れれば、家族も守れなくなります。
自分のことだけ考えていれば良いという時代ではありませんし、「今だけ、金だけ、自分だけ」という人が増えたから、今の社会になっているとも言えるでしょう。
ただ、私の場合は、日本の危機をなんとかするために、自分のことを後回しにし過ぎてバランスを欠いていた(異常事態だったので自覚しながらもやってきた)ので、遺品整理などもできるように、と思っています(やらないといけないことは山のようにある)。
私の「志事」
①店 日本の伝統工芸・職人さんを守る、応援する
②美術館 父の作品をご覧いただき、「世界の保坂紀夫」「世界の美術史上最高傑作」という評価が広まるように
③講演会 八方良しの実現、皆が幸せに暮らせるように 国防
④コミュニティ 繋がって循環させることで、地域の仲間を守る、地元を元氣にする
⑤ほんもの寺子屋 国の根幹である教育を根本的に変え、子ども達が幸せに生きられるように、日本を守る
⑥かいまみ(情報誌) 山梨の人物・お店・イベント・お勧めの本など紹介 山梨の人の表現の場 啓蒙など
⑦勉強会 暮らしや社会を良くしていくために学び続ける
⑧ブログ・FB投稿 大事なことをお伝えする
⑨私生活 エコな暮らし、お金やモノを地域・国内で循環させる実践
以前、講演を聴いた方から、「弟子を取ったほうが良い」と言われ、「弟子」なんて考えたことがなかったのでびっくりした、と投稿したことがありました。
弟子という形でなくても、私がやっていることの価値を認めてくださり、同じ志を持ち、同じ方向へ進んでいきたい人達と力を合わせて、生きていければと思います。
でも、私の弟子になりたい、なんていう奇特な人はいるのかな~?(笑)