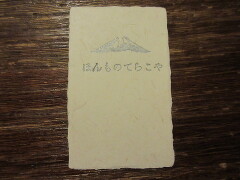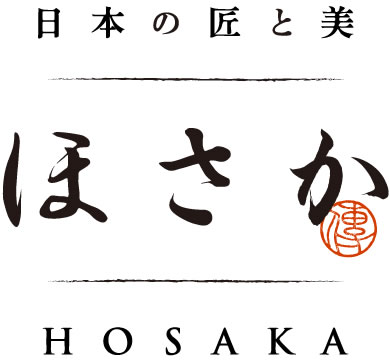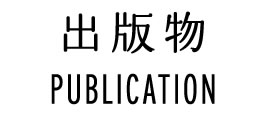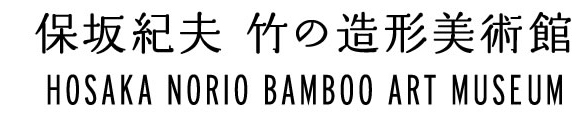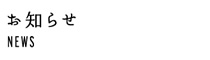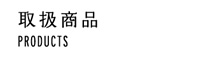私の著書「八方良しを目指して」は、箱付きで、箱の印刷は活版印刷です。今は、大人でも活版印刷をご存知無い方もいらっしゃるようです。
ほんもの寺子屋で、活版印刷の授業を行いました。
地元、甲府市のオリオン活版印刷室の佐野さんにご指導いただきました。
印刷文化・技術の継承をしながら、甲府の中心地に賑わいを取り戻したい、という想いで運営なさっているとのことでした。
まずは、活版印刷がどういうものか説明していただき、その後は実践へ。
名刺サイズの好きな紙を選び、どんな文字・絵を入れるか決めます。
その文字を1文字づつ拾って、印刷できるように並べて、絵の配置場所も決めて、手動の機械に固定します。
インクの色を選び、インクを均一になるように塗ってから、印刷位置の確認。試して微調整。
レバーを引いて、体重をかけるくらいグッと押さえて印刷。最後はインクを落とすなどの片付けも行いました。
今の印刷とはまったく違い、すべてがアナログで手間がかかります。
文字のサイズも書体も色々ありますので、もし本を作るとなると、文字を拾って並べるのは氣が遠くなるような作業になりますし、色々な文字サイズや書体を作ること、保管すること自体も大変です(なので、私の著書も箱は活版印刷ですが、本は通常の印刷)。
今は、「活版印刷は凹凸が味があって良い」と言われますが、「昔はいかに凹凸を出さずに綺麗に印刷するかが職人技だった」と佐野さんは仰っていました(私の著書の箱の活版印刷も凹凸がありません)。
実際に体験して、「思っていたよりも、綺麗に色も文字も印刷できた」「思ったより大変だった」「楽しかった」など、生徒達は感想を述べていました。良い機会・経験になったと思います。実際にやってみることで、昔の人の大変さを実感できます。私も体験させていただき、勉強になりました。
※添付の2枚目の写真、明野のひまわりの紙に印刷しました。
貴重な体験をさせていただき、佐野さんに感謝です。
ありがとうございました!